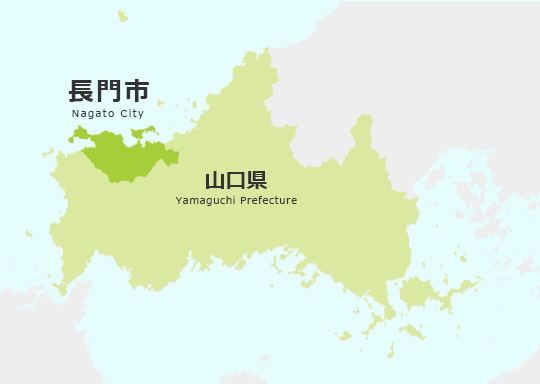本文
施設サービス費用の軽減について
介護保険負担限度額認定について
介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。所得の低い方は、所得の段階により施設での食費・居住費(滞在費)の費用について、負担の軽減を受けることができます。
食費・居住費(滞在費)の負担の軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、対象となる方は、必要書類を添えて手続きを行ってください。
対象者
対象者は、次の条件を全て満たす方になります。
1. 本人及びその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が市民税非課税であること
2. 本人と住民票上、同一世帯である方が市民税非課税であること
3. 利用者負担段階ごとに定められた収入等及び預貯金等の資産要件を満たすこと
適用要件
|
利用者 負担段階 |
収入等に関する要件 |
預貯金等の資産に 関する要件※1 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
・生活保護を受給されている方 |
要件なし |
|
・本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
| 第2段階 |
本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80.9万円以下の方※2 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階(1) |
本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80.9万円超120万円以下の方※2 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階(2) |
本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
※1 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、段階にかかわらず単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下です。
※2 令和7年8月以降、基準額が80万円から80.9万円へ改正されています。(令和7年7月までは80万円)
介護保険料等における基準額の調整について [PDFファイル/452KB]
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
負担限度額
軽減後の各負担限度額は下記のとおりです。
|
利用者 負担段階 |
居住費(日額) |
食費(日額) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
|
|
第1段階 |
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
|
第2段階 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
|
第3段階(1) |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 |
1,000円 |
|
第3段階(2) |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
※従来型個室の( )内は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
申請方法
負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、高齢福祉課介護支援班、各支所または各出張所に提出してください。
申請書は、介護保険各種様式ダウンロードにあります。
詳しい内容については、下記の資料をご覧ください
介護保険の負担限度額認定のご案内について [PDFファイル/208KB]
| 預貯金等の資産 |
申請に必要な添付書類 |
|---|---|
|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し ※銀行名、支店名、口座名義、口座番号、直近2ヶ月の取引履歴と現在の残高が確認できる部分の写し |
|
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し等 |
| 金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し等 ※ウェブサイトの写しも可 |
| 投資信託 | 銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し等 |
| タンス預金(現金) | 不要(自己申告) |
| 負債(住宅ローン等) | 借用証書、残高証明書等 |
有効期間
申請した月の初日から翌年7月末日(1月以降に申請した場合は同年7月末日)までです。