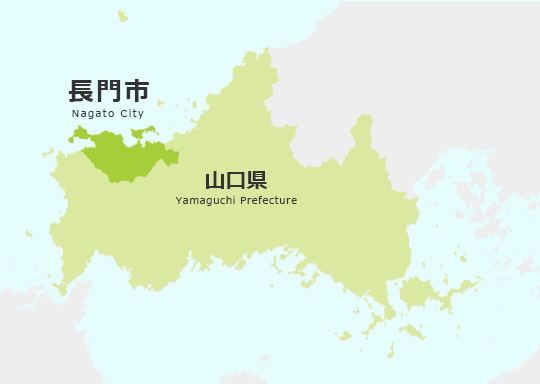ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
~江戸時代から続く伝統行事~仙崎祇園祭






7月20日(土曜日)から26日(金曜日)まで、仙崎の八阪神社で仙崎祇園祭が行われました。
仙崎祇園祭りは、江戸時代初期から続く伝統行事で深川の赤崎祭り、油谷の人丸祭りとともに「大津三大祭り」の一つと言われています。
八阪神社前の山車の上では、笛や太鼓、かねを使って「祇園ばやし」が奏でられ、子どもたちの踊子が舞を披露し、祭りの神様が乗った山車とともに「疫病退散」を願いました。舞子の華麗な日本舞踊に、地域住民からは大きな拍手が送られました。
また縁日では、やきとりやかき氷、射的、スーパーボールすくいなどのお祭りではおなじみの店舗などが出店され、子どもたちは仙崎で楽しい夏の思い出を作りました。
仙崎通り町協議会副会長の早川さんは「祭りに、家族連れや若い人達がこんなにもたくさん来てくれて本当にうれしい。仙崎の若いメンバーが、盛り上げようと一緒に頑張っている。祭りを通して、色々なつながりができているので形が変わったとしても今後も続けていきたい」と話していました。
最終日の26日には、地元有志による「仙崎祇園花火」が打ち上げられました。