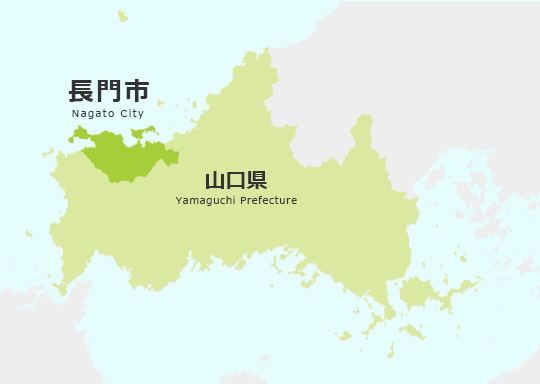ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ





本文
今年も地域による慰霊を〜麻羅観音供養祭が開催〜





5月3日(火曜日)、俵山地区にある麻羅観音で供養祭が執り行われました。
昨年に引き続き感染症対策として来賓の出席や出店などのイベントは行われませんでしたが、能満寺の住職による読経の後、地元自治会関係者ら約10人が焼香をし、慰霊を行いました。
昨年の慰霊祭に参加した宇部市の江嶋さん親子が今年も参加。昨年は子宝に恵まれたお礼を兼ねて訪問し、今回はすくすくと成長したお子さんと一緒に焼香を行いました。
供養祭の締めくくりに、麻羅観音保存会の三浦代表が「3年前から式典のみの供養祭の開催となりさみしく思っています。しかし、多くの方にお参りをいただいている実感があります。また、今回の供養祭にも昨年も足を運んでいただいたご夫婦と、成長し歩けるようになったお子さんの姿を見て感激しました。お参りする方のことを考えると、この供養祭をこれからも続けていきたいです。1日も早い新型コロナウイルス感染症の収束を願っています」と述べました。
供養祭は毎年5月3日に開催されています。麻羅観音の敷地の清掃など、地元による管理が行われています。
<麻羅観音の由来>
天文20年(1551年)9月1日、中国地方の太守大内義隆公は家臣の陶晴賢に攻められ、長門湯本温泉の大寧寺で自刃しました。大内義隆公の長子の義尊公は、翌2日、この奥にて捕らえられ惨殺されました。末子の歓寿丸は女装して、俵山の山中にかくまわれていましたが、翌年春捕らえられ、麻羅観音のある場所にて殺され、男児の証拠に男根を切られて持ち去られました。これを里人は哀れみ、この社をたてて霊を慰めました。
麻羅観音には子宝に恵まれたい人や健康増強への願いを託す参拝者が多く訪れています。