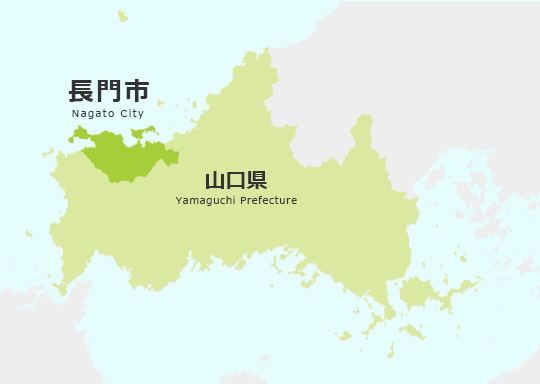ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
江戸時代からの伝統を次世代に~滝坂神楽舞~






県指定無形民俗文化財(国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財)に指定されている滝坂神楽舞が、11月2日(火曜日)、三隅滝坂地区の黄幡社で奉納されました。
滝坂神楽舞は、1764年(明和1年)の黄幡社建立当時に、3年間続く大飢饉と牛馬の疫病を免れようと、厄払いの祈願のため神楽を奉納したのが始まりとされています。現在、滝坂神楽舞保存会により保存・伝承されており、毎年11月2日の午後8時から舞が行われています。昨年と今年は、新型コロナウイルス感染症の影響から保存会の関係者のみでの開催となり、全24演目のうち9演目が披露されました。
神を迎える場を清める「足均」から舞が始まり、神の居所を探す「尉」、神の威力が滝坂の地に幸せをもたらすことを示す「手力男」などの舞が続きました。終盤には、松明を手に持って舞う「火の舞」が披露され、神が真剣で綱を断ち切る「神明」、「舞おさめ」で幕を閉じました。
今年新たに演者として加わった内田凪飛さんは、「小中学生の時には演じていたが、久しぶりに踊ることができて改めて文化を守る大切さを感じました。昔から守られている文化を誰かがつないでいくことが大事だと思います。今後も続けていきたいです」と演じ終えての感想を話してくれました。
また、滝坂神楽舞保存会の柳谷哲二会長は「新型コロナウイルス感染症の影響で練習があまりできないなか、自治会の皆さんの協力で今年も開催することができたことに感謝しています。昨年は6演目、今年は9演目でしたが、来年からは子どもにも舞ってもらい、演目も増やせればと思います。」と語りました。