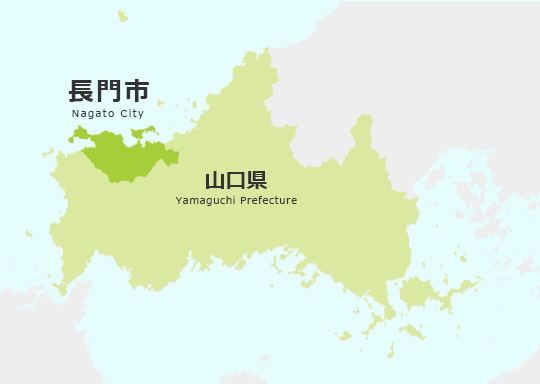ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
伝統の女踊り~真木の大歳神社で君が代踊りの奉納~






11月15日(日曜日)、真木の大歳神社で君が代踊りの奉納が行われました。
君が代踊りは古くから奉納されていましたが、明治時代になると公演も少なくなり、衰退していきました。これを昭和38年に郷土史家の山崎徳三郎氏が、君が代踊りの貴重性に着眼して踊りの復活を試み、当時唯一謡を覚えていた岡崎竜馬氏と唯一踊りを知る尾崎ユキ氏の協力を得ながら、仙崎の幼稚園長であった角谷スミ氏が新たに振付をし直し、赤崎山で行われた山口国体で披露したことでよみがえり、現在まで引き継がれているものです。
かつて11月18日に真木まつりを行っていたことから、現在ではその直前の日曜日に、毎年大歳神社で奉納されています。
君が代踊りは男性用の振り付けを女性が躍るという特徴があり、この日は真木地区の女性11人が衣装に身を包み、太鼓、鉦、踊りに分かれて奉納を行いました。
昭和38年の踊りの復活から昨年まで56年間にわたり、君が代踊りを奉納した村田喜久子さんは、「君が代踊りは一度途絶えたものを復活して引き継いできたもの。民謡の全国大会に出場したり、平成6年には伊勢神宮にも奉納した。次の世代の人に引き継いでもらいたい」と話していました。
真木地区では一年を通して、毎週水曜日に踊りの稽古をしているということです。