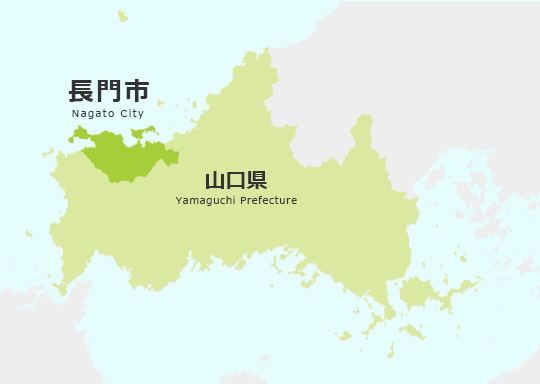ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
防災を熟議で考える






熟議を行うことで防災意識の高揚を図ろうと、12月25日(木)、「長門みすゞ学園の防災教育を一層進めるための次の一手を考える」が長門市物産センターで開催されました。今年8月6日から8日にかけて、宮城県南三陸町への研修視察に参加した市内中学生と公民館職員が熟議に参加しました。 冒頭、大西市長が、「夏休みに南三陸町を訪問したみなさんの体験談を聞きました。まさに、みなさんは防災のスペシャリストになったと思います。そのような経験を、各中学校のみすゞ学園の中でどう活かすかが大切です。身の回りには自然災害だけでなく登下校時の交通安全や、実際に不審者による声かけなどの事案が発生している中、自分の身は自分で守るということに(その経験を)活かしてほしいと思います」とあいさつしました。 開会行事のあと、菱海中の2人の生徒により南三陸町の視察報告が行われました。南三陸町の被災現場のようすが3年前の被災直後から変わっていないところと、整備が進んでいるところとの差に気がついたことや、最後まで避難を呼びかけながら津波に飲まれた防災庁舎へ訪れたことなどが報告されました。また、現地の避難している人から直接話を聞いたことについても報告されました。 続いて、各中学校2校ずつ3つのグループに分かれて、防災に取り組むには何が必要か、熟議が行われました。それぞれが大きな紙に、付箋紙で防災の備えができていること、そうでないこと、地域と学校との関係などについて意見が述べられ、課題について意見をまとめました。 最後にグループごとに次に自分たちの身を守るために必要なことは何か、発表が行われました。その中で、地域のつながりを普段から作っておくことや独居の高齢者の存在を確認したり、電柱に避難場所の表示を至る所でつけておくことや防災グッズを学校に備えておくことなどが提案されました。 参加した中学生は、真剣に意見を出し合い、「南三陸町での経験を今後多くの人に伝え、活かしていきたい」と話していました。