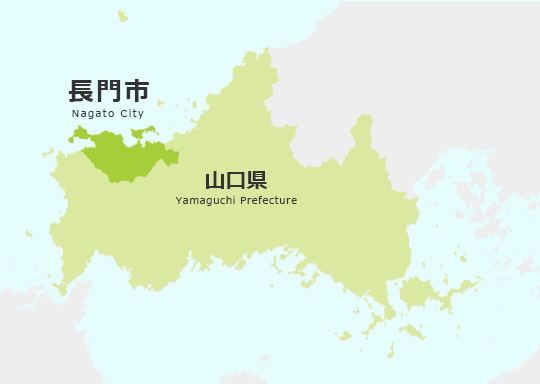ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
俵山麻羅観音で法要






5月3日(火)11時から、俵山の麻羅観音堂で供養祭が行われました。天文20年(1551年)9月1日、中国地方の太守、大内義隆公が家臣の陶晴賢に攻められ、湯本温泉の大寧寺で自刀しました。末子の歓寿丸は女装して山中にかくまわれていましたが、翌年春捕らえられてここで殺され男児の証拠に男根を切られて持ち去られました。これを里人はあわれんで、この社をたてて霊を慰めたことが麻羅観音の始まりとされています。-1" color="#ffffff 能満寺住職による読経が行われる中、関係者が焼香を行いました。参拝者には紅白餅が配られ、地元の有志による焼き鳥屋台や飲み物が出店されていました。また、法要後、地元の方々による踊り(大内哀史、俵山温泉囃子)が奉納され、最後に盛大に餅まきが行われました。contents attach