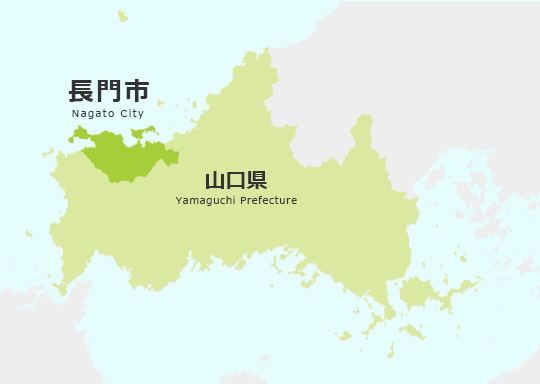ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ






本文
サバーサマがご出陣!






7月3日(金)、サバー送りが飯山八幡宮を出発しました。サバー送りは稲の害虫を防ぐための虫除けの年中行事で、毎年田植えの終わった6月の終わりから7月の上旬にかけて行われています。引き受けは、上郷、江良、藤中、中山の4地区が輪番で担当しており、今年は江良地区の人たちが、藁と竹で作られた2体の騎馬武者人形、サバーサマとサネモリサマを境川を経由して日置地区の長崎の隧道まで運びました。サバーサマは、稲の害虫ウンカが神格化したもので、サネモリサマは源平合戦で討ち死にした斎藤実盛を指すといわれています。斎藤実盛は篠原の戦い(石川県)で、稲の切り株に足をとられ討たれてしまい、その怨念が稲の害虫になったという伝説から来ているとされています。 ここからは、黄波戸、古市、久富、人丸、河原、伊上を経て、下関市豊北町へ入り最後は湯玉の犬鳴岬から「サバーサマ、カラヘイケ!」と唱えながら海に流されるそうです。地区から地区へは主に子どもたちが「サバーサマオークレ、サネモリサマオートモヨ」などと歌いながら運んでいくということです。この行事が終わると本格的な夏がやってきます。