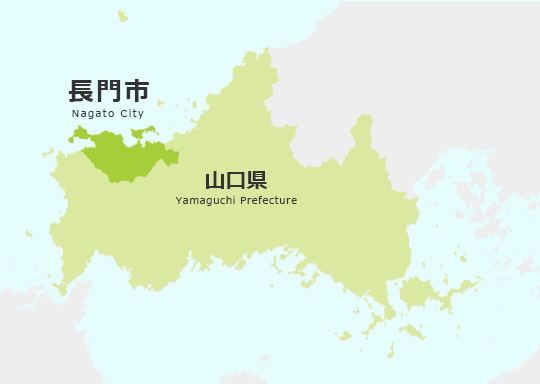本文
空き家に付随した農地が取得しやすくなりました
空き家に付随した農地の取り扱いについて
移住を希望する方々の中で「農業をやってみたい」という希望をお持ちの方もありますが、農地を売買・贈与する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
その許可の要件として、農地法第3条では、許可後に耕作する面積(下限面積)が「50a(5,000平方メートル)以上になること」とされていました。
※ 本市では、油谷向津具上、油谷向津具下及び油谷川尻地区において下限面積を10a、それ以外の地区においては30aとしていました。
これらの根拠となる法令(改正前農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号)が削除されたため、下限面積の要件によらず許可を受けることができるようになりました。
ただし、今後も他の許可要件を満たすことは必要です。
詳しくは農地の売買、贈与、賃借等の許可ポイントをご覧ください。